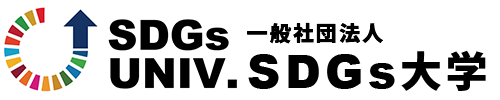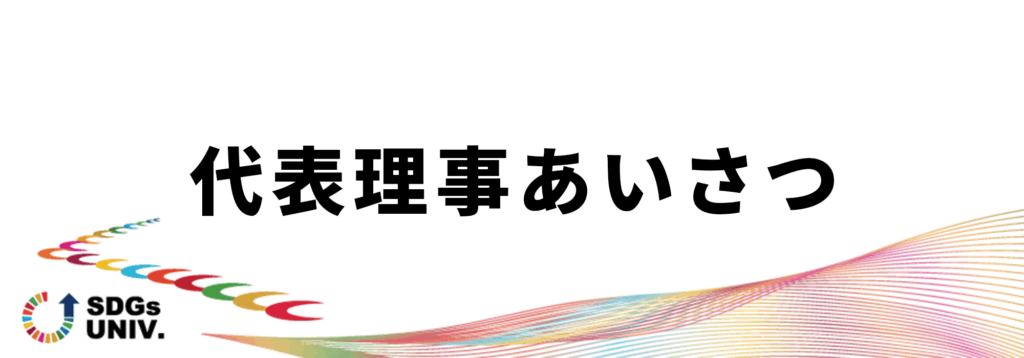

誰一人取り残さない未来へ
SDGsは人づくりの挑戦でもある
SDGs大学 代表理事 清水 一守(しみず かずもり)
KAZUMORI SHIMIZU
持続可能な開発目標(SDGs)とは、193の国連加盟国が2015年9月、
ニューヨークの国連本部で開催された「持続可能な開発サミット」 で正式に採択されたアジェンダ(行動計画)を指します。
それは17の目標と169のターゲットで構成され、2016年1月1日よりスタートし、 2030年12月31日を達成予定としています。
SDGsは、ミレニアム開発目標(MDGs)の成果を土台としており、
「将来の世代がそのニーズを満たす能力を損なうことなしに、
現在のニーズを満たす開発」と定義されました。
その達成のためには経済成長、社会的包摂、環境保護という3つの核となる要素の調和を欠かせないものとし、
SDGsはこれら3つの面をカバーしています。
私がこのSDGsに出会ったのは、2015年7月30日です。
東京財団のCSR白書2015の出版記念において、米コロンビア大学地球研究所所長、
国連事務総長の特別アドバイザーのジェフリー・サックス氏と考える持続可能な開発と企業の社会的責任の場でした。
その中で彼は、 ミレニアム開発目標(MDGs)よりも持続可能な開発目標(SDGs)のほうが達成することは難しいと述べていました。
当初は理解できずに何となくCSRのガイドラインのようなものと思い込んでいましたが、
17の目標と169のターゲットを一つずつ読み解いていくと、SDGsは壮大な目標であり、
企業だけではなく世界の一人一人が問題解決に取り組んでいく必要があると感じました。
日本は戦後、ララ物資、ケア、ユニセフなど、世界から数多くの支援を受けてきました。
その支援金額は今の価値に換算すれば1兆3,000億円を超すとされています。
また、世界銀行からの多額の支援は、日本の奇跡的な復興の元になっています。
現在日本はGDPが世界第4位、人口1億2375万人で世界第14位、
領土、領海、 EEZ(排他的経済水域)を合わせた面積は世界第6位となっています。
途上国と言われた時代から進化・発展し先進国・大国となりました。
今、私たちはこのような恩恵を授かったことや資源国家であることを再認識し、
「だれ一人取り残さない」社会を実現すべく「世界の国づくり」と「人づくり」に貢献していかなければなりません。
当大学はSDGsにおいて国内外で活躍する人たちを応援・育成し、SDGsを実現するための活動を行っております。
代表理事 清水 一守(しみず かずもり)
プロフィール
一般社団法人 SDGs大学 代表理事
岐阜県出身 日本大学文理学部卒
大学は体育を専攻し古橋広之先生(フジヤマノトビウオ)に師事
卒業後家業である食品販売店を継ぐも新聞販売店に経営転換。
地域のまちづくりとして中山道赤坂宿のブランド化を推進。
その後、CSRの重要性を学ぶ。
2018年7月より名城大学にて月に2階の勉強会「東海SDGsプラットフォーム」を開催(現SDGs大学プラットフォーム)。
2019年にSDGsを広めるための認定資格講習を開催。
現在もSDGsの普及と達成に努める。
資格: 英語CMIサスティナビリティ(CSR)プラクティショナー資格 / 相続診断士